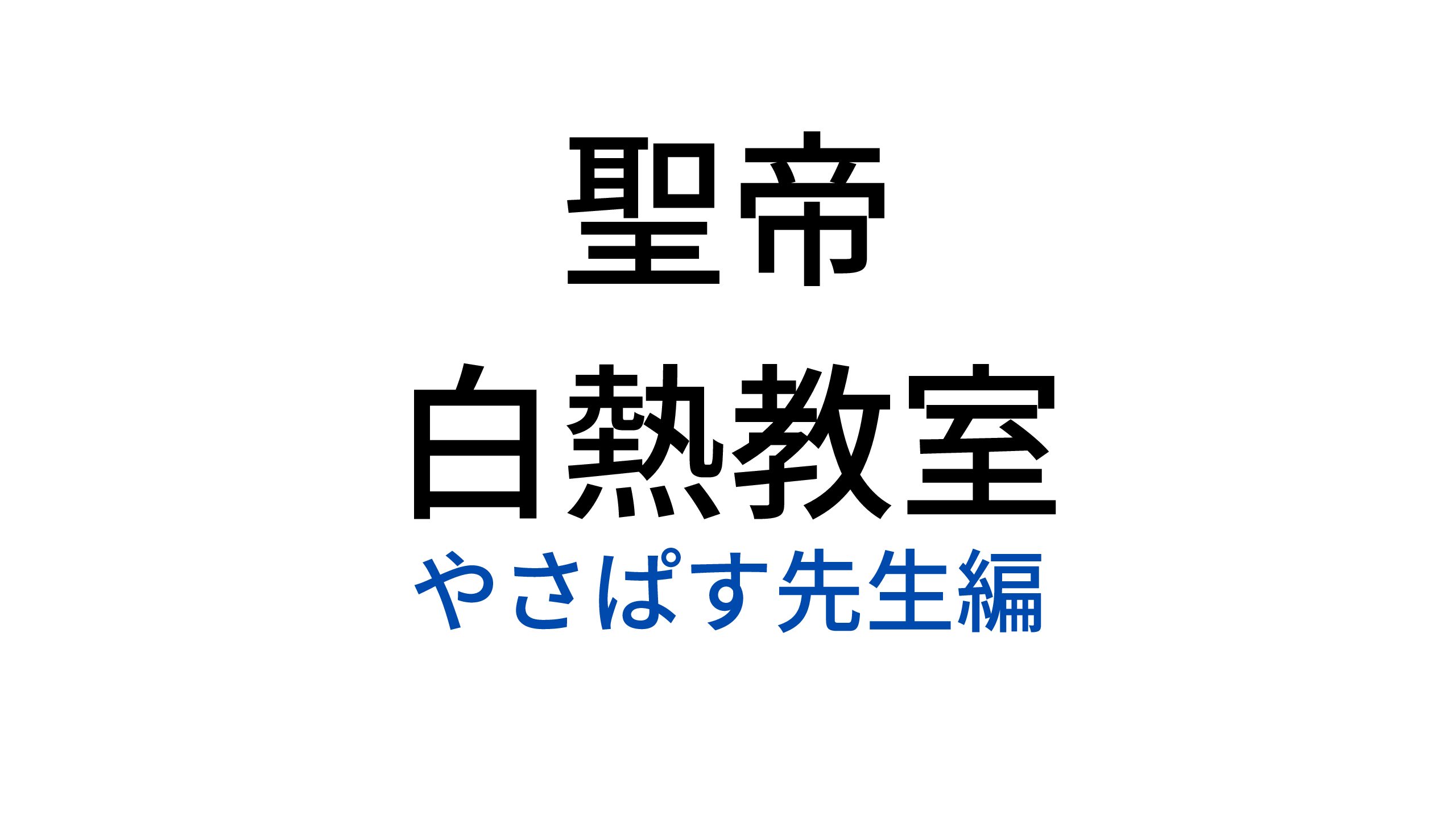読書感想記事。
昭和39年(1964年)から連載開始された作品で、上・中・下巻の3巻構成となっている。
家康三部作 概要
聖帝サウザー師匠は以前より「司馬遼太郎先生の徳川家康三部作は名作だ」と、リスナー各位に推奨していた。
先日、『覇王の家』の上下巻を読み終わったので、続いて関ヶ原を読み始めた。
その時わかったのだが、実は覇王の家という本は最初の本ではなかった。
発行順は下記だった(初版発行年)。
- 関ヶ原(1966年)
- 城塞(1971年)
- 覇王の家(1973年)
オイオイ僕は最新作から読んじゃったのか、と思った。
しかし『覇王の家』は家康の幼少時代からその最期までを一気通貫で語った伝記というスタンスであり、独立した内容だったので、問題なかった。
今回、『関ヶ原』の上巻まで読み進めたが、『関ヶ原』は家康だけではなく石田三成に関しての描写も多い。
まず家康の一生をダイジェスト版として知りたい人には、やはり覇王の家から入っていくのがよいと思う。
読む前までの理解
まず、僕がこの関ヶ原を読む前までに持っていた知識とイメージについて説明しておきたい。
皆さんは、関ヶ原の戦いと聞いて、何を知っているだろうか。
もちろん、大河ドラマや映画、歴史の漫画をよく読んでいる人にとっては背景がよくわかっていると思うのだが、
学校の授業で勉強した程度の知識の僕はこんな感じだった。
- 織田信長が本能寺の変でやられる
- 豊臣秀吉が後継者争いに勝って天下人になる
- 豊臣秀吉が老衰で没し、後継者争いが勃発。秀吉の子供を擁する石田三成と徳川家康が戦った(関ヶ原の戦い)
- なお西軍には裏切り者がいた模様
- 負けた豊臣家は滅んで、家康が征夷大将軍に任命されて江戸時代へ
これくらいの解像度だった。
特に、勝者として時代を作っていった徳川家康が主人公で、負けた石田三成は敵役のイメージでいた。
ただ、正義とか悪とかではなくて、戦国時代の雰囲気で、弱肉強食の結果、家康が天下を取ったのだと、そのくらいの理解でいた。
石田三成に関しては全然知らなかった。
花の慶次に登場する、厳格な奉行というイメージしかなかった。
実際、この『関ヶ原」』においても石田三成は厳格な奉行だった。
そして彼は意外にも、主人であった秀吉に対して並々ならぬ恩義を感じて、忠義を誓って行動していた。
僕はそれまで、石田三成という人は冷静沈着な官吏であり、その立場のために豊臣家代表として戦ったのだと思っていたのだが、そこには熱い忠義の心があったのだ。
正義マンは嫌われる
そんな石田三成は、どこまでも真っ直ぐな人だったようだ。
不正を許さず、正義を遵守して、それに違反したものを厳しく取り締まっていく。
三成の行動は全て理にかなっていて、ぐうの音も出ないほどの正論だった。
そのため、彼は敵が多かった。
戦国時代というのは、まだまだ前時代であり、人治政治だった。
その時代において正義とか清廉さを全面に押し出す三成は、諸侯から煙たがられる存在になってしまった。
このようなことは、戦国時代でなくても現代日本においても似たようなところがある。
正論を正論として突きつける側は、その正当さゆえに攻撃的になれる。
消費税がテイクアウトとイートインで分かれたときに各所に出現した「正義マン」は、まさしくこれだろう。
正義マンは、確かに正義で正論なのだが、その正義でもって堂々と人を攻撃してしまうところが危うい。
正義だから、正しいから、反論できない。
これが危ない。
絶対的安全圏からの、容赦なき投石。
これをやられた方は反撃不能であり、ただただ投石をその身に受ける。
まさに「ぐぬぬ」である。
そして、徹底的にやられた後はーー
恨みを持つ。
絶対に復讐してやると誓う。
これが危ない。
この感情を持たれてしまうことがとても危ない。
石田三成は、この辺の感情の機微を察知することに疎かったようだ。
というか、知っていながらも、それをうまく扱えない、扱いたくないという子供っぽさがあった。
一方の徳川家康は正反対で、この人の機微をうまく使いながら味方を増やしていく。
もし、もし仮にだが、石田三成がそんなに正義マンではなく、人当たりが良くて敵を作りにくい性格であったなら、家康の天下取りは難しかったかもしれない。
(とは言え、いろんな言いがかりをつけて豊臣家を追い詰めていくと思われるが…)
厚遇は感動になる
僕がこの上巻を読んで特に印象に残ったことは、先の
「正論で人を打つと恨まれる」ともう一つ、
「力ある人の厚遇は感動になる」だった。
家康は味方を増やすために色々と工作をするのだが、そのやり方がとても丁寧なのだ。
ただ単に形式が丁寧なだけではなく、そこには「心」が宿っているように”見える”。
なぜ”見える”という言葉を使うのかといえば、それは真心でそうやっているのではなくて、謀略のための厚遇であるからだ。
しかしその厚遇を受ける側の武将たちはそこまで考えが及ばずに
「私のような下の者に、徳川殿はここまでの厚遇をしてくれるのか!
なんとありがたい…太閤様亡き後の我があるじは、徳川殿がいいな!」
というなんとも素直な感じ方をして、家康に心服していくのだ。
「これ何か裏があるんでないか?」と思う者は少なく、皆、割と素直に味方になっていくのだが、そこが家康の巧さであろう。
というか、当時で最高峰の実力がある大名に厚遇されたら、そりゃ大抵の大名はなびくよな、とも思うのだが、絶対的正義をかざす豊臣家の守護者・石田三成が「正義マン」で恨みを買いまくっているせいでこの調略もうまくいくのであった。
「調略」耐性の獲得
僕はこの一連の調略を見て、感じた。
雇われ人の仕事をしていると、このように厚遇をちらつかせて懐柔しようとしてくる奴がいることに。
「ボーナスはずむから」
「昇進が早くなるから」
「キミの今後のためだから」
と勤め先の上司たちは、部下を懐柔しようとする。
エサをぶらさげて、無理させようとしてくる。
実際、エサをくれることもある(少ないが)。
それをうれしがって、うれションしてしまうような労働者に、なってはならないのだ。
僕はかつて若き頃、ブラック勤務時代に、社長からの厚遇に感動して忠誠を誓った。
薄給でも、犬馬の労を厭わず休日サービス出勤とサービス夜間作業を捧げた。
そういう「精神的報酬」は自分の持ち物(時間・労力)を無償で捧げさせてしまう力を持つ。
今思えば、バカな若者だった。
が、しかし当時は社長の厚遇がうれしくてたまらなかったのだ。
そんなことを、この『関ヶ原』(上)を読んで思い出していた。
本作を読めば、調略をかける側の考え方を垣間見ることができる。
それを知っておけば、今度は安易に調略されることはなくなるだろう。
「調略」に対して「耐性」を得られる。
そこが僕個人として、上巻で得られたものだった。
これから中巻に入っていくので、また読み終えたら感想を書いていこうと思う。